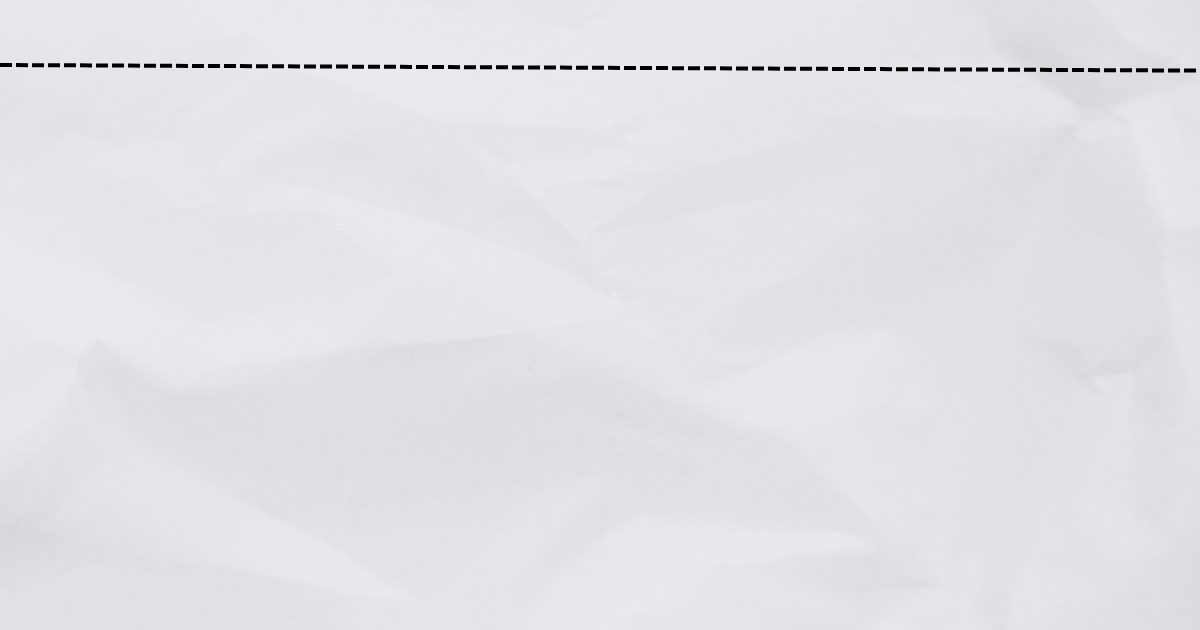クッキーは上手に焼けた。亜沙のアイデアで生地にレーズンとピーナッツを混ぜこんだのが正解だった。あと十枚は味見したいところをぐっとこらえて袋に詰めると、 ピンク色のリボンで口を結んだ。
翌日、山崎シュン君は亜沙が「これ食べて」といって差しだしたクッキーを「いらないよ」と突き返した。
手作りのクッキーにまつわる思い出、ありますか? パペログ給仕長のパペレオンです。
今回は、今村夏子の短篇集より表題作「木になった亜沙」をご紹介します。
あげようとする食べ物を誰にも受け取ってもらえない女の子の物語です。
亜沙があげるものは誰も食べない
こんな話です。
主人公・亜沙は、大好きな母と祖母と暮らす元気で心優しい女の子です。一見、ごく普通の子供に見えますが、彼女にはひとつ、みんなと違う点がありました。 それは、亜沙が差し出す食べ物を、誰ひとりとして口にしようとしないということです。 お母さんが炒ってくれたひまわりの種。 亜沙はとても気に入ったのに、友達にあげようとしても食べてもらえません。 転校していく山崎シュン君のために頑張って作ったクッキーは受け取ってもらえず、給食当番で盛り付けたインゲン豆のサラダには、クラスメイトの誰も箸をつけてくれません。 人間だけではないのです。金魚は亜沙が与えた餌を食べず、お腹を空かせているはずの野生動物でさえ、亜沙のポケットのお菓子を無視します。 そう、亜沙が手ずから与えようとする食べ物は、例外なく拒絶されてしまうんです。 時は経ち、体を壊した母の入院が長引き、祖母には妄想の症状が現れます。叔母夫婦に引き取られた亜沙は、子のいなかった夫妻に赤ちゃんが生まれたあと、育児を手伝うようになります。でも、何度も悲しい思いをしてきた亜沙は、赤ちゃんにミルクを与えることだけはしませんでした。 そんなある日──。
ここから、亜沙の運命は予想もしなかった方向へ転がっていくのですが、幼少期から徹底的に繰り返される拒絶の描写には胸が痛みます。
「食べること」と「生きること」はもちろん密接に関わってきますし、亜沙が差し出す食べ物は彼女の繋がりを求める気持ちや愛といったものを象徴しているのでしょう。
それなのに、亜沙があげるものは誰も食べない。
こんな孤独と断絶の描き方があるのだなと思いました。
料理について詳しく
考察
転校していく男の子、山崎シュン君に渡そうと亜沙が作ったのは、レーズンとピーナッツ入りクッキーでした。
ちなみに日本レーズン協会が2019年に実施したアンケート調査では、レーズンをあまり食べない(半年に一回以下の頻度)という人が61.7%おり、その理由としてレーズンの味または食感が苦手であるためと回答した人が53.5%に上りました。つまり全体の約33%の人がレーズンが苦手という結果になったわけです。
他方で、LINEリサーチが2021年にチョコレートについて実施したアンケート調査では、「あまり好きではない」「まったく好きではない」という回答は合わせて6%に留まりました。
何が言いたいかというと、クッキーに混ぜこむものとしては、レーズンとピーナッツって少し人を選ぶ感じがするということです。チョコレートとか、ナッツにしてもアーモンドやクルミのほうが無難じゃないかなあ。
個人的にはそのあたりが、空回りする亜沙の無邪気な善意を象徴しているかのように感じたため、今日の一品に選びました。
まあ、シュン君はどんなクッキーであろうと受け取ってくれなかったのだと思いますが。
彼は、「ピーナッツもレーズンもクッキーも苦手だ」と言いました。そんなことがあるでしょうか?
恐らく、差し出してきたのが亜沙だからなのです。ただ盛りつけただけの給食のサラダすらクラスメイトに拒絶される亜沙。「亜沙だからダメ」なんです。ピーナッツもレーズンも、「亜沙だからダメ」にしてしまったのです。
「どうして?」「なんで私はダメなの?」「どうしてみんなと違うの?」という亜沙の声が聞こえてきそうです。
物語の転調
物語の後半では、「亜沙だからダメ」という前提が思わぬ形で崩れ、亜沙の差し出す食べ物を受け取ってくれる人が現れます。
この「転」から結末に至る流れは、物悲しく、相変わらず理不尽でありながら、不思議な赦しと安らぎに満ちています。食べること、生きること、誰かを受け入れ、誰かに受け入れられることの難しさと愛しさで溢れているように感じました。
今村夏子の世界
「レーズンとピーナッツのクッキー」の微妙な感じに触れましたが(もちろん好きな人もいると思います!)、今村夏子って、何とも絶妙に美味しくなさそうな料理を描写するのが上手いんですよね。
「父と私の桜尾通り商店街」で、主人公が売れ残りのコッペパンに自宅の残り物や手作りの惣菜を挟んで作るサンドイッチとか。美味しそうなのもあるんだけど、水分がしみてグチュッとしそうだなと思ったり、果ては髪の毛が混入してたり。
愛とか料理、誰かの口に入るものって、まあ大雑把に言えばいいものじゃないですか。一応そういうことになってはいる。でも今村夏子作品ではそう単純にはいかない。
不条理で悲痛な現実、世界中から拒否されているかのような生きづらさを生きる人々を、今村夏子はこれまでも一切の綺麗事なく描いてきました。
短篇集「木になった亜沙」は、一見すると著者のそれまでの作品より、ファンタジー的な意味での幻想的な要素が強いように思えます。
人が木になり、さらなる変貌を遂げる表題作。
主人公よりむしろ周囲の人間が精神に異常をきたしてしまったかのような「的になった七未」。
そして、語り手が人間であることを今ひとつ確信できないまま、不安のうちに読み進めることを強いられる「ある夜の思い出」。
これまで読んできた今村作品は、むしろ本短篇集をわかりやすく「翻訳」したものだったのではないかと、読み終えて感じました。
描きたいことを幻想的な描写で書いたのではなく、著者にとって世界とは、まさしくこのように奇怪であり得ないことの塊なのかもしれません。
「変形」のあとの世界の姿こそ、現に誰かが見ているこの世界そのものなんです。陳腐な表現かもしれませんが、今村作品には、小説の真髄を突きつけられる気がします。
さて、今日はほろ苦く端っこの焦げたようなクッキーをお届けしました。
亜沙のクッキー、あなたは受け取ってあげられそうでしょうか?
パペログ給仕長 パペレオン