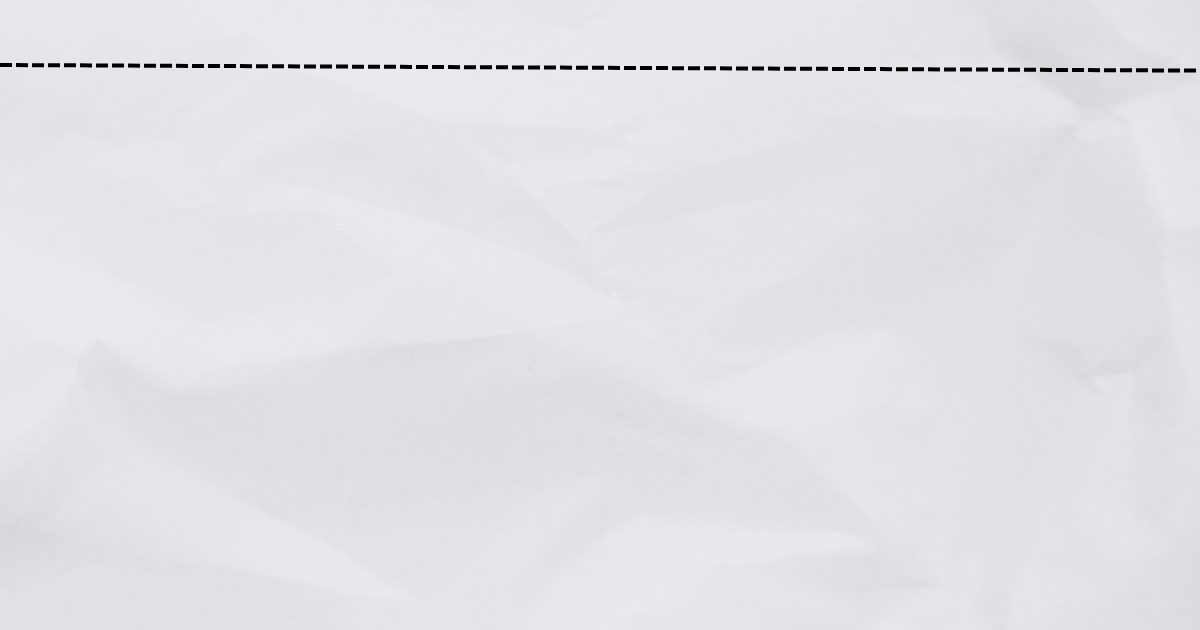しろくまちゃんが まぜます
こむぎこ おさとう ふくらしこ
こなは ふわふわ ぼーるは ごとごと
だれか ぼーるを おさえてて
232刷320万部発行の大ベストセラー絵本(2020年10月時点)
ふわふわのホットケーキは子供も大人も大好き。何枚も重ねてあって、溶けかけのバターや蜂蜜がトッピングされていたらもう最高ですね。パペログ給仕長のパペレオンです。
そんなホットケーキをおやつに作ろう! と、可愛らしいクマのキャラクターが取り組む様子を描き、1972年の刊行以来ずっと愛されてきた名作絵本「しろくまちゃんのほっとけーき」。
本記事では、しろくまちゃんの愛らしい料理風景や絵本としての魅力に触れつつ、本書が時を超えて子供たちに愛される理由をご紹介します。
「しろくまちゃんのほっとけーき」が長年愛され続ける理由
個人的な思い出話で恐縮ですが、私自身、子供の頃は「しろくまちゃんのほっとけーき」が大好きでした。
自分で読めるようになってからも、ほかほかのホットケーキの味を想像しながら繰り返し読んだものですが、実は母によると、もっと小さいうちから子供たち(3人きょうだいです)にせがまれて何度読み聞かせしたかわからないという思い出の本だそうです。
それこそ、一日に何度となく「読んで読んで」とねだられるので、文章もすっかり覚えてしまい、料理などで手が離せないときには、キッチンからそらで読み聞かせをしていたそうです。
子供たちをとりこにする「しろくまちゃんのほっとけーき」。
文章の作者、森比左志さんは、下記のポイントを押さえて内容を工夫し、本書を作成したと巻末に寄せています。
「しろくまちゃんのほっとけーき」のねらい
ホットケーキの絵本をつくりながら、こどもが開いて歓喜する姿を想像しました。
それは、①大きなホットケーキを食べるうれしさ② ホットケーキができる過程への興味 ③自分でつくるということの魅力などです。
なるほど、しろくまちゃんのホットケーキ作りはまず道具と材料を揃えるところから始まり、自ら手を動かして一生懸命焼きあげていくというものです。
冒頭に引用した、材料をかき混ぜるシーンでは、ボウルが揺れて中身が周辺に飛び散る様子が描かれています。しろくまちゃんはまだ小さいから、大人のように片手でボウルを押さえながら器用にかき混ぜることができないのでしょう。徹底的に子供の目線で描かれていることがわかります。
そして、物語中盤のもっとも盛り上がる場面は、フライパンの中でホットケーキが焼けていく丁寧な描写です。
フライパンへ落とした生地にぷつぷつと小さな穴ができ、固まってきて、ひっくり返すと綺麗な焼き色がついている。おいしそうな匂いがしてきて、湯気がたって……。
そんな様子が、心躍る楽しい擬音と共に描かれています。
最後は、仲良しのこぐまちゃんを呼んで二人で分け合い、おいしく食べます。友達と食べるおいしさは格別。さらに、自分が作ったものを友達に振る舞うことの何と誇らしいことでしょうか。
「しろくまちゃんのほっとけーき」を赤ちゃんの頃から楽しめる理由
日に何十回という読み聞かせを厭わず、とことん付き合ってくれた母のおかげもあってか、大変な本好きに育った私ですが、子供が生まれてごく初期に買い揃えた絵本のうち一冊が、この「しろくまちゃんのほっとけーき」でした。
個人的な思い入れもあったのですが、生後2ヶ月頃から赤ちゃん用の絵本を何冊か読み聞かせした結果、本書は低月齢の乳児でも充分楽しめると思えたからでもありました。
まず、赤ちゃんはコントラストが強い鮮やかな色彩や左右対称の図形が大好きです。多くの赤ちゃん用絵本は、この点を押さえて作成されています。
たとえば、Sassyの赤ちゃん絵本「にこにこ」には、赤や黒、はっきりとした青色、黄色などの鮮やかな色が使われています。これは母が書店で見かけて「これは良さそうだわ」と思って買ってくれたものですが、生後2ヶ月の我が子も食い入るように見つめていました。
また、赤ちゃんは繰り返しの擬音など、耳に心地よい音やテンポが大好きです。赤ちゃん絵本の定番として推薦されることが多い「じゃあじゃあびりびり」や「がたんごとん」などがその典型で、前述のSassyシリーズも「ぽんぽん」「ちゃぷちゃぷ」といった繰り返しの擬音で構成されています。
では、「しろくまちゃんのほっとけーき」はどうでしょうか。
わかやまけんさんによる作画は、太い主線と鮮やかな色遣いが特徴的です。「しろくまちゃんのほっとけーき」は表紙からして鮮やかなオレンジ色。コップに入った水は青、ホットケーキの焼き色は焦げ茶色といった具合で、かなりはっきりした塗り分けがなされています。ホットケーキやしろくまちゃんたちのキャラクターデザインが左右対称というのもツボを押さえています。
また、ホットケーキが焼ける場面では「どろどろ」「ふくふく」といった擬音や、「やけたかな」「まあだまだ」といった心地よいリズムのセリフが使われています。
以上から、「しろくまちゃんのほっとけーき」は赤ちゃんにも好まれる要素を押さえていると言えるかと思います。実際、生後5ヶ月の時点で我が子の興味を惹くことができていました。
低月齢のうちは、物語がわかるわけではありませんから、子供が興味を持つページを広げて、楽しい擬音を聞かせてあげるだけでも充分でしょう。大人が絵本を支えるので、ボードブックでなくても案外破かれたり舐められたりせずに済みます。
赤ちゃん向けに特化して作られた絵本と異なり、自分で読んで楽しめる年齢まで、長く様々な楽しみ方ができる点も魅力です。早いうちから手に取る価値のある絵本だと考えます。
(余談ですが、子供時代の実家には優に千冊を超える絵本があったので、私の絵本集めの旅はまだまだ始まったばかりです。)
料理について詳しく
さて、せっかくなので、しろくまちゃんのホットケーキ作りを体験できるようにレシピを考えてみたいと思います。
考察
もっとも、ホットケーキのレシピはたくさんありますし、しろくまちゃんが使う材料はごくシンプルなものですから、あまり工夫の余地はありません。
しろくまちゃんが集める道具はボウルにフライパン、最後にホットケーキを盛りつけるための大きなお皿。かき混ぜるための泡だて器、焼くときに使うフライ返しもイラストの中に登場しています。
材料は卵、牛乳、小麦粉、ふくらし粉、砂糖。これだけわかれば充分です。
レシピ
【材料(こぐまちゃんと分け合うための4枚分)】
- 卵・・・・・・・・・1個
- 牛乳・・・・・・・・3/4カップ
- 小麦粉(薄力粉)・・・200グラム
- ふくらし粉(ベーキングパウダー)・・・小さじ2
- フライパンに引く油・・・適量
- バター、はちみつなど・・・お好みで
【作り方】
- 薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖を合わせてふるう
- ボウルに卵を割りほぐし、牛乳を加えて混ぜる
- [2]に[1]を加えて混ぜ合わせる
- フライパンに油をひき、中火で加熱する
- いったん火から下ろし、濡れ布巾にフライパンの底を押し当てる
- フライパンを弱火にかけ、生地の1/4量を中央へぽたあんと流し入れる
- 表面にぷつぷつと小さな穴があいてきたら、少し待って裏返す
- いい香りがしてきたら、焼き上がり
- お皿に移して、一緒に食べたい人を呼びましょう
【工夫ポイント】
- ホットケーキミックスを使わなくても簡単です。粉類は合わせてふるうか、泡だて器でかき混ぜて。
- 濡れ布巾に加熱したフライパンの底を当てることで、温度が均一になり、むらなく綺麗な焼き色に。
- めくってみたくなっても我慢して。表側3分、ひっくり返して2分が目安です。
- 家族や友達と分け合えばいっそうおいしく。もちろん、独り占めしてもかまいません。
- バターやはちみつ、メープルシロップ、好きなものをかけて召し上がれ。
おまけ:「絵本の積み木」でしろくまちゃんのほっとけーきの世界をより楽しもう
子供が生まれてから、絵本選びのため足繁く通うようになった書店で、「絵本の積み木」というものを見つけました。
「はらぺこあおむし」や「ノンタン」「11匹のねこ」など、人気の絵本のキャラクターや小道具をモチーフにした、彩色の木製積み木です。
「こぐまちゃん」シリーズからは「しろくまちゃん」と「こぐまちゃん」、「しろくまちゃんのほっとけーき」セット(単品のしろくまちゃんとは違う服のしろくまちゃん、フライパン、ホットケーキ×4枚)が発売されています。
赤ちゃんの頃から「しろくまちゃんのほっとけーき」の色鮮やかなイラストや楽しい擬音に親しみ、少し大きくなったら、一緒にホットケーキを焼いたり、積み木で絵本の世界を再現するごっこ遊びをしたりするのも楽しそうですね。
もちろん、「こぐまちゃん」シリーズファンの大人の方にはインテリアとしてもお勧めです。
以上、少し長くなりましたが、子供たちの夢とワクワクがたくさん詰まった「しろくまちゃんのほっとけーき」のご紹介でした。
それではどうぞ、童心にかえって召し上がれ。
パペログ給仕長 パペレオン